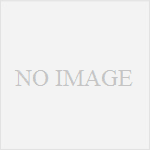
『「ゲームの歴史」を書いた筆者岩崎夏海』氏ってどっかで聞いたと思ったらもしドラの人っぽいな
『「ゲームの歴史」を書いた筆者岩崎夏海』氏ってどっかで聞いたと思ったらもしドラの人っぽいな 知らんけど ついでに別件のPCエンジンのつぶやきも目についたんで またひとつ賢くなってしまいました
Twitterライクにつぶやく、働きたくねぇ.comの分家サイトです
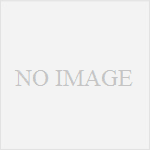
『「ゲームの歴史」を書いた筆者岩崎夏海』氏ってどっかで聞いたと思ったらもしドラの人っぽいな 知らんけど ついでに別件のPCエンジンのつぶやきも目についたんで またひとつ賢くなってしまいました
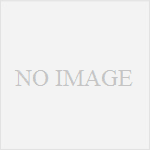
これが本当の逆転の発想なのか、私気になります またひとつ賢くなってしまいました
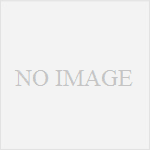
兵は死地なりだからシャバの人間に選手の気持ちは分からないのかもしれんな (感じ方には個人差があります) ちなみに、兵は死地なりって廉頗が趙にいた頃の話だったのか そうなると、長平の戦いの結果は趙括が現場を知らないことが原因だったのか、私気になります (諸説あります) ついでに、廉頗は刎頸の交わりの元ネタで、その相手の相如は完璧の人だったのか またひとつ賢くなってしまいました
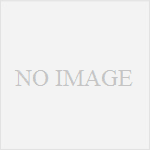
これで油はね・酸化しない原理が、私気になります 家にある梅干しを入れて揚げ物をするだけで油はねが防止でき、かつ油も酸化しないという驚きのワザ。梅干しを2つ程いれるだけで、油がキレイになるんです!
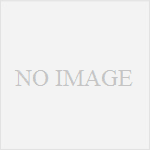
笑っちゃうふんわりラップのかけ方も知らない○年も生きてきたのにねだったのか、私気になります またひとつ賢くなってしまいました
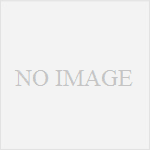
ドーナツの穴にはそんな歴史があったのか またひとつ賢くなってしまいました
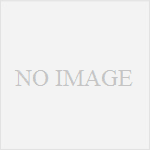
なんか、昔のアニメで「ふられ気分でRock'n' Roll」のカバーが使われてたのを思い出したんだが ググったら「せんせいのお時間」だった 今更知ったけど、これカバーしてるDROPSってすげえ豪華メンバーだな しかも、DROPSがなければAice5が存在しない時間軸もあったのかもしれんな またひとつ賢くなってしまいました ついでに思い出したんだが、「EQUALロマンス」もカバーされてたよなと思ってググったら、こっちは「デ・ジ・キャラットにょ」だった EQUALロマンスは本家CoCoのも「らんま1...
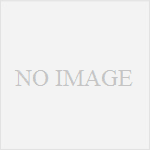
「人に話したくなる土壌微生物の世界」らしい 賀大名誉教授の染谷孝さん(67)が、26年間の研究成果をまとめた「人に話したくなる土壌微生物の世界」(築地書館)を出版した。
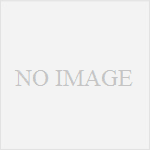
昨今のLGBTがーからは反発されそうだが、江戸時代から男の自殺は止めないのが武士の情けだけど女の自殺は止めろと言われてるし、これはこれで結果オーライなんじゃね 知らんけど ちなみに、江戸時代の話だけど今までソースが見つからなかったが見つかったかもしんない これ見て「江戸時代の橋守り」の線でぐぐったらそんな感じっぽいな ちなみに時代劇でよく目にする橋からの身投げだが、当時は実際によくあったらしい。『半七捕物帳』の著者・岡本綺堂によると、両国橋の橋番は基本的に身投げを救わない方針をとっていて、女の場合は引き留めるこ...
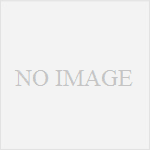
持ち株が100倍ぐらいになって家を建てようと思った時に役に立つかもしれんな 知らんけど